第15話 鰻のフライで恋人毒殺
『ロード・ランドル』("Lord Randal", Child 12A)
 |
| Illustrated by Arthur Rackham, from Some British Ballads (1919). |
これは母親と息子の会話だけで成り立っている歌です。帰って来た息子の母親が「どこへ行ってたの」とたずねる。息子は「緑の森へ行ってきました」と答えるが、続けて「母さん 床をのべてください/狩りで疲れました ぼくは横になりたいのです」と言う。繰り返される息子の願いを無視して母親は質問を続け、息子が答える:「そこで誰に会ったの」→「恋人に会いました」、「その娘(こ)は何をくれたの」→「鍋(なべ)で揚(あ)げた鰻(うなぎ)のフライです」、 「食べ残しは誰が食べたの」→「鷹(たか)と猟犬(いぬ)が食べました」、「鷹(たか)と猟犬(いぬ)はどうなったの」→「脚を伸ばして死にました」。これを聞いた母親の応対は一変する:「おお おまえは毒をもられたのです」と言うと、息子はあっさり「そうです 毒をもられたのです」と認める。と同時に、横になりたい理由が「胸が苦しい」からだと変化する。この後、母子の間で不思議な対話が続く。「母さんには何をのこすつもりかい」と聞かれて、息子は「二十四頭の乳牛をのこします」と答え、「妹には何をのこすつもりかい」には「金と銀をのこします」と答え、 「弟には何をのこすつもりかい」には「ぼくの館(やかた)と領地をのこします」と言う。そして最後に「恋人には何をのこすつもりかい」と聞かれて「地獄の 業火(ごうか)をのこします」と答える。
母と子の対話が普通の意味で成立しているのは各スタンザの1行目前半と3行目前半(上に引用した質問と答え)だけで、残りの大部分は同じ言葉の繰返しであることが一見して解る。対話は緩やかに、しかし、徐々に緊張感を高めてゆく。その間、たずねる母親の側でも、答える息子の側でも、ただならない事態を前に感情の表現はゼロである。対話はただ淡々として、ほとんど無味乾燥のまま、気配としての緊張感が第5スタンザ(鷹と猟犬が脚を伸ばして死んだという答え)で クライマックスを迎える。ところが、毒をもられたという真相を前に、依然として二人の調子は淡々として変わらない。わずかに「狩りで疲れました」('I 'm weary of hunting')というリフレインが「胸が苦しい」('I 'm sick to my heart')と微妙に変化するだけである。この後のやり取りは「臨終口頭遺言」 と呼ばれるものであるが、先行する普通の遺言内容と著しく性質を異にする言葉が最後に「遺言」という形を借りて盛り込まれる。「地獄の業火(ごうか)をのこします」——これはもはや「遺言」ではなくて、毒を盛られて今死にゆこうとする彼の、恋人に対する怨念、呪詛とも言うべきものである。それまでの対話を一切の感情表現を抜いて、ただ淡々と進行させることで、最後の一点に感情を凝縮した感じである。他のバラッドでもしばしば登場するこの手法は、臨終口頭遺言詩という中世の詩形式を利用したバラッドの物語技法が生み出した抜群の効果と言えよう。
ロード・ランドルは「鍋(なべ)で揚(あ)げた鰻(うなぎ)の フライ」が毒だったと言うが、ウナギそのものに毒性は無く、食べ過ぎると心筋梗塞を引き起こすという。好物のウナギの食べ過ぎが原因で死んだ教皇マルティヌス四世(在位:1281-85)のことはダンテの『神曲』煉獄篇第24歌にうたわれている。ロード・ランドルがこの歌の状況でウナギを食べ過ぎたと考えるのは多少無理があり、むしろ、ここではウナギと偽って毒蛇を食べさせられたと考える方が分かりやすい。はっきりと「ヘビ」('snakes')とうたっている版も多い。
ひとくちアカデミック情報: 臨終口頭遺言: 「臨終口頭遺言」('nuncupative will')というのは、もともと中世の「遺言詩」と呼ばれる形見分けの歌の形式で、代表的な例は、中世フランスの詩人ヴィヨン(François Villon, 1431-after 1463)の『形見分け』(Le Lais)や『遺言書』(Le Testament) である。一例を挙げると:「一つ、グリニーの領主殿には/ニジョンの城の護りを委ねて/他に、モンティニーより六匹多い猟犬と/ヴィセートルの館と塔を贈る/また、あの乱暴者、鬼っ子、/領主を訴訟狂いさせてるムートンには/あぶみ革で三打ちと/足枷はめてゆっくりお休みの権利を贈ってやる」(「ヴィヨン の形見分け」15、天沢退二郎訳『ヴィヨン詩集成』白水社、2000)。贈り物の品々は、手袋、帽子、長靴、薪、炭、エンドウ豆の塩豚煮込、手鏡、古着、 松葉杖、ズボン下等々、種々雑多である。中世の人々には、その所有物の一切を、どんなにつまらないものまでも、ひとつひとつ、丹念に、遺贈する習慣があっ たそうである。(J. ホイジンガ『中世の秋』堀越孝一訳、中央公論社、1971年、430ページ参照。)これがバラッドの物語技法として取り込まれ、殺人事件の真相を暴露する時に登場する「常套表現」となったのである。
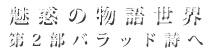



コメント
このコメントの RSS