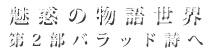第89話 矮小化されるロビン・フッド一味
「リトル・ジョンの物乞い」 ("Little John a Begging", Child 142B)
前話でも紹介したように、州長官や修道院長など体制側の欺瞞と悪を暴くことにこそ自らのレーゾンデートル(存在理由)があると公言するロビン・フッドがいる一方で、それは決して支配する体制側だけの問題ではないとする視点がちゃんとあること、バランスのとれたその視点があってロビン・フッド物語は成功しているということを述べておきたい。
今回の歌では、主人公はロビン・フッドではなくて、部下のリトル・ジョンである。ある日、ロビンがジョンに物乞いに行くように命じる。「物乞いに行けというのなら」と不満げなジョンは、「巡礼の僧の服を着て/杖とコートと袋を持ち/・・・/パンを入れる袋をくだされ/チーズを入れる袋もくだされ/金を入れる袋もだ/施しの品を無くさぬように」と、乞食(こつじき)としての立派な身支度を要求する。
 |
| 陣内敦作 |
道中、「聾(つんぼ)や盲(めしい)や跛(びっこ)の四人の乞食(こじき)」に出会う。[以下、本文および訳文において差別用語的表現をしている箇所があるが、これらは、歌がうたわれた時代の状況をできるだけ忠実に描写するため、また、日本語の調子のために使用したものであり、偏見に基づくものではないことをお断りする。] 仲間に加わろうと何くれとなく話しかけるジョンの無知を連中は馬鹿にする。弔いの鐘が鳴って人が処刑される様子をジョンが「なぜ鐘が鳴り響く/犬の首吊りとは如何なるものか/・・・様子を探ろう」と言うと、乞食の一人が「犬の首吊りではない」と教え、「人が死んで 我らはチーズとパンにありつける/おまけに 施しもいただけるのだ」と言い、自分たちのような仲間はロンドン(イングランド)にも、ベリック(スコットランド)にも、世界中にいるのだと、現実を教えるのである。「とっとと失せろ 腰曲がりの阿呆(あほう)」と罵られて、1対4の喧嘩になる。勿論ジョンは圧倒的に強いのである。しかしここで、ジョンは更なる厳しい現実を目撃することになる。「ジョンにつねられた唖(おし)は大声を出し/目の見えない盲(めしい)と/七年前から足の悪かった跛(びっこ)は/ジョンより速く走って」逃げ出す。結局ジョンは四人をつかまえて打ちのめし、「ガンガン壁に押し付けると/金貨がジャラジャラ」鳴り響くのである。何と、乞食たちの袋の中から「一生かかっても使い切れまい」と思うほどの、合わせて六百三ポンドもの大金をジョンは仕留めるのである。シャーウッドの森に帰ったジョンは、ロビンと仲間たちの出迎えを受ける。首尾良い物乞いの報告を受けた彼らは、手を取ってオークの木のまわりをうたい踊ったという。
ロビンが悪代官や修道院長から大金を召し上げて大ご馳走にうたい騒ぐ場合とは、しかし、(少なくとも、読者にとっての)後味がいささか違うのではなかろうか。確かに、弱者のふりして私腹を肥やす者たちが槍玉に挙がっているかも知れないが、彼らにはそこまでせざるをえない現実もあっただろう[これを書きながら、筆者は第二次大戦後の正に同じ街角の風景を思い出している]。一方、まっとうな乞食(こつじき)の修業行脚を通してではなく、有無を言わせない力関係で彼らの(汗と涙の?)収穫を横取りして祝宴を上げるというのは、悪代官たちとさほど違わないようにも感じてしまう。
乞食とロビンたちの出会いをうたった更に二つの作品についても簡単に紹介しておきたい。一つは『ロビン・フッドと乞食 その一』 ("Robin Hood and the Beggar, I" 133)、もう一つは『ロビン・フッドと乞食 その二』 ("Robin Hood and the Beggar, II" 134)である。前者は、ロビンが乞食に打ちのめされた後、着るものを交換して乞食に変装したロビンが、例によって笛の音で集めた三百人の部下の射手の力を借りて、処刑されようとしていた三人のヨーマンを代官から取り戻すという話である。後者でも、ロビンが通りで出会った乞食に思う存分打ちのめされる。死んだものと思い込んだ乞食が意気揚々と引き上げた後、たまたま通りかかった三人の手下の者たちからロビンは助けられる。「襤褸(ぼろ)を纏(まと)った乞食めに/よもや負けるとは思わなかった」とうそぶくロビンは、「この俺を頭(かしら)と慕っておるならば/行って仇をとってこい」と命じる。「奴に気づかれる前に/不意打ち食らわせるのだ」と、かつての正々堂々とした戦いの精神とはほど遠い指示を出す。三人に襲われて、棍棒を奪われた乞食は、自分がなぜ襲われたのか解らないが、窮地を脱するために知恵を絞る。「もし私をお見逃しくださるならば/・・・/・・・金貨百ポンド差し上げます/それ以上の銀貨も差し上げます」という誘いに乗ったロビンの手下は、乞食を逃してやることにする。約束の金をずだ袋から出そうとする際に、巧みに袋が風下になるように地面に置く。中には大量の小麦粉が入っていた。乞食は、両手にずだ袋の端を持って、一気に中の小麦粉を奴らの顔に撒き散らす。目潰しを食らった彼らはほとんど何も見えず、棍棒でしたたか打たれた挙句、一目散に逃げ帰る。命からがら森にたどり着いた彼らにロビンは、「我らが面目は丸つぶれ/二度と拭(ぬぐ)えぬ面汚し」と罵るのである。最後は、「ロビンは受けた屈辱を/決して忘れはしませんでしたが/二人が自分と同じくあの棍棒の味を舐めたことで/顔もほころんでくるのでした」と締められるが、英雄像が甚だしく矮小化された感は否めない。
それは、やはり時代の変遷と深く関わっていると捉えるべきか。天真爛漫な無法者一味が卑小化してゆく姿に自らの姿を写さざるをえなくなった近・現代人が、郷愁の念を込めてロビン・フッドの物語を愛して止まないと言っては言い過ぎだろうか。
ひとくちアカデミック情報:
ヨーマン:yeoman. 中世イギリスの独立自営農民。15世紀のイングランドでは封建貴族の勢力が衰退し始め、それまで農奴と呼ばれ、荘園領主から貸与された土地を耕作して賦役貢納などの義務を負う身分であった農民が解放されて自立していった。没落した封建貴族と農民でも豊かな層はジェントリ(gentry、郷紳)となり、中間層の独立自営農民がヨーマンリー(yeomanry)、その下に零細な没落農民というように三つの階層に分化した。
*データ管理上の都合により、コメント欄はしばらく非公開にさせていただきます。どうぞご了解くださいませ。