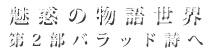第100話 差別の連鎖
「リズィ・リンズィ」 (“Lizie Lindsay”, Child 226B)
ハイランドの若者が、「エディンバラの町へ/花嫁を探しに行かせてほしい」と母親に言うと、「行ってらっしゃい/花嫁を連れていらっしゃい/でも お世辞で求婚してはだめ/貧しい暮しぶりをちゃんと伝えなさい」という忠告を受ける。若者はローランドの首都エディンバラにやってきて、若い娘たちの踊りの場に加わりながら、リズィ・リンズィという娘が一番気に入り、「僕の恋人になってくれ/そして一緒に/ハイランドへ来てほしい/・・・ハイランドでは/チーズとヨーグルトを食べさせてあげる/ベッドは緑のシダでこしらえて/僕のプレードが二人の掛け布団」と、さっそく求婚に及ぶ。(「プレード」とは、ハイランド人が身に着ける格子縞ラシャの長い肩掛け。)ハイランドがどこなのかも相手が誰かもわからないというのに行けるわけがないでしょうと拒否するリズィに、若者は「僕の父さんは年老いた羊飼い/母さんは年老いた酪農婦/僕の名前はドナルド・マクドナルド、と説明する。「僕は一国一城の主/国の王様にも負けるものか」と、クランのプライドを誇示し、「なあリズィ ハイランドへ行こう/そして一緒に小羊の世話をしよう」と迫る。高貴な身分の騎士であるリズィの父親がやって来て、「お前がわしの娘を盗もうものなら/即刻 縛り首にしてやるぞ」と脅す。しかしリズィの侍女は、自分だったらドナルドと一緒に行くと言い、リズィが「あなたは宝石箱や/きれいなシルクのスカートを投げ出して/裸足の貧しい男と一緒に行って/両親もみんなも捨てられるというの」と言うと、侍女は「だって あの男(ひと)は魔法使いかもしれない/もしかしたらすごい身分かも/私ならあのドナルドと一緒に行くわ/どんな運命が待っていようとも」と、どこまでも積極的である。納得したリズィは「シルクの外套を脱ぎ/侍女のガウンを身に着けて/遥かかなたハイランドへと/この若き羊飼いとともに旅立った」のであった。
 |
| 陣内敦作 |
谷を越え、山を越え、靴はぼろぼろになったリズィは、若者についてきたことを後悔する。出迎えた母親は、「お帰りなさい サー・ドナルド/よく帰ってきたわね」と言い、若者は「サー・ドナルドなんて呼ばないで/息子ドナルドって呼んでくれよ」と応じるが、二人の会話はエルス語(ハイランド地方で話されるゲール語)だったので、「リズィにとってはちんぷんかんぷん」である。翌朝、陽が昇るまで眠っていたリズィは、牛の乳絞りを手伝ってくれ、と起こされる。目に涙を浮かべたリズィは、「ああ エディンバラに戻りたい/ハイランドなんか絶対いやよ」とつぶやく。山の高みに連れて行き、遠くまで続く広大な景色を見せながら若者は娘にこう言ったという:「僕はこの島々 そして山々の主なんだ/君は今やその地主の美しい花嫁だ/だからハイランドへ来たことを嘆かないで/僕と来たことを悲しまないで/今や君は偉大なマクドナルド家の立派な夫人/生涯 マクドナルド家の奥方様だ」・・・リズィがどう応じたかは語られない。
類似の設定で「グラスゴーのペギー」(‘Glasgow Peggie’, Child 228)という作品があるが、いずれの場合も対立の構図は「豊かなローランドに対する貧しいハイランド」である。首都エディンバラや、そこから北西に16マイル、旧ファイフ州南西部の都市ダンファリンには歴代スコットランドの王の居城があり(第12話参照)、西には鉄鋼造船業などで栄えた経済文化の中心地グラスゴーがある。対して、ハイランドとは岩山だけの不毛の大地である。
「民衆」(「フォーク」)という言葉に嫌悪感を覚えると放言した英(イングランド)文学者がいたことは忘れ難いが、18世紀のイングランドにおいて「文壇の大御所」と呼ばれたサミュエル・ジョンソン(Samuel Johnson, 1709 - 84)は、イングランドの文学者であると同時に『英語辞典』(1755年)の編纂で知られる。英語辞書の先駆けとなった功績はともかく、この辞典を有名にしたのは、その特異な言葉の定義にあった。例えば、‘lexicographer’(辞書編集者)とは、「文章を書き写し、言葉の意味を説明するという仕事をこつこつとこなす無害の人」とあるが、‘oat’(オート麦)を「イングランドでは一般に馬に与えられ、スコットランドでは人が食べている」と説明して有害とは考えなかったようである。これが、彼個人だけの差別意識ではなかったからであろう。もともとイングランドとスコットランドは別々の独立国家であったとか、片やアングロサクソン民族、片やケルト民族という血の対立も原因の一つかも知れない。例えば、「ジョニー・スコット」(‘Johnie Scot’, Child 99A)で、王に仕えて禄を得るために麗(うるわ)しのイングランドの城に行ったジョニーが王の娘と仲良くなって子供ができ、その噂が王の耳に入ったことを、「一人娘のお腹(なか)の中に/いやしいスコットランド人の子がいる」と表現される。この種の例には枚挙に遑(いとま)がないが、今回話題の「リズィ・リンズィ」や「グラスゴーのペギー」では、ローランドがハイランドを軽蔑するという、同じスコットランド内での差別の構図である。物質的に豊かなものが貧しいものを軽蔑するという図式は、ある意味人類そのものが今日まで絶えることなく繰り返してきた差別の歴史である。(アメリカで台頭してきた白人至上主義、世界各地できな臭くなってきた全体主義、日本国内における一極集中と地方の疲弊、それらはすべて同根の現象である。)
ユーチューブというウェブサイトの登場がバラッドの復活を促しているという感を日々抱いており、今日ではチャイルド・バラッド306篇のすべてを聴けるようになったが、中で今回の「リズィ・リンズィ」が124点以上あるというのは、例外的に多く驚くべき数である(「以上」というのは、同じ一人の歌い手がこの歌を異なった場面でうたっているものが複数あるということ)。みんな、貧しいハイランドへの応援歌である。かつて、1960年代にジョウン・バエズ(Joan Baez, 1941- )らがベトナム反戦フォークソングの一種としてチャイルド・バラッドをうたってバラッド・リバイバルを生み出した。バエズは父がメキシコ人で、母がスコットランド系で、幼い頃から人種差別を体験したこともあって、ベトナム反戦運動のみならず、広く公民権運動、中東その他世界各地での紛争解決のための活動を続けているが、彼女にとっての伝承バラッドは、体制と権力の対極にあった民衆の心情を最も良く伝えるものとしてあったのであろうか。
ひとくちアカデミック情報:
ユーチューブ:YouTube. 「歌の箱2」はRaymondcrooke氏(第35話の「ひとくちアカデミック情報」参照)による歌であるが、氏は2カ月前にチャイルド・バラッド306篇のすべてをうたい遂げるという快挙をなされた。第96話で報告した陣内敦氏による全挿絵完成と正に期を同じくした偉業である。
「魅惑の物語世界」と題した私のバラッド・トークも今回で第100話に辿り着いた。チャイルド全篇のほぼ三分の一をカバーしたことになる。「バラッド」という、日本ではまだまだ馴染みの薄い物語世界をどこまで噛み砕いて紹介できたかは判らないが、一応今回をもって私の独りトークも幕引としたい。今後は、「バラッド詩」(第11話の「ひとくちアカデミック情報」参照)と呼ばれる、イギリスの詩人たちが伝承バラッドに魅せられて残した自らのバラッド作品を紹介してゆきたい。ただし、今までのように毎月1回と規則正しくではなくて、不定期に、制作年代順も無視して、気の赴くままに、私が魅惑されて止まない世界を逍遥したいと思う。
*データ管理上の都合により、コメント欄はしばらく非公開にさせていただきます。どうぞご了解くださいませ。