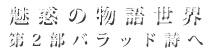第73話 「生娘」へのこだわり
「ギル・ブレントン」 ("Gil Brenton", Child 5A)
前話で、生娘(きむすめ)で国に帰れることに感謝するという最後の台詞は下手な付け足しのように思われると書いたが、実は多くの作品でどういうわけか生娘(きむすめ)へのこだわりがバラッドの物語の一つの大きなモチーフになっていることも事実なのである。古今東西、それは男のエゴの証明かも知れないし、被害者の女性の最後の勝利でもって男の愚かさを証明するものであるかも知れないし、女性の勇気を積極的に証明するためであるかも知れない。数ある中から、そのような作品を 二、三紹介してみよう。
 |
| 陣内 敦 作 |
「ギル・ブレントン」なる名の王様が、海のむこうに使いをやって「緑の森の高貴な女」に結婚を申し込み、花嫁として迎えることになったという。馬を牽く小姓に向かって花嫁が、これから参る国の慣わしを教えてくれと言うと、小姓は「優しい女は/その慣わしを嫌います」と言って、待ち受ける恐ろしいしきたりを告げる。王様は今までに七人の王女と結婚し、寝床を共にしながら、いずれもその後乳房を切り取って、嘆く王女たちを里へ送り返した、というのである。小姓は、「あなたがお城の門に着いたとき/王さまの母君が 金の椅子を用意して/生娘かそうでないかを試そうと/日が暮れるまで あなたを椅子に座らせます/あなたが確かに生娘ならば/無事に花婿のベッドにゆけるでしょう/あなたが生娘でないならば/侍女に代りをお頼みなさい」と告げるのであった。生娘でないものが坐ると滑り落ちるという魔法の椅子である。花嫁が五百ポンドで侍女に身代わりを頼んだということは、すなわち、花嫁は生娘ではなかったのであった。
王様と美しい侍女が寝室で横になった時、あくまでも生娘にこだわる王様は「毛布よ答えよ シーツよ答えよ/頭の下の枕よ答えよ/ぼくが娶(めと)ったのは生娘なのか/ぼくが寝たのは生娘なのか」と問いかけると、その魔法のシーツ等が、「あなたが娶(めと)ったのは生娘じゃない/でも あなたが寝たのは確かに生娘」と答える。事実を知った王様が母君のところに行って事情を訴えると、その母君は真相を確かめようと、扉を破って女の部屋に踏み込んでゆく。女が語るところによると、ある日、リンボクの実を拾い、赤いバラとタイムを摘むために緑の森に行くと、「どこかの王子さまのよう」なハンサムな若者が現れたという。続く言葉にこそ、この歌の重要な暗示があるように思われる:「生娘かそうでないかも構わずに/日が暮れるまで 彼はわたしを離しません/生娘かそうでないかも構わずに/日が沈むまで 彼はわたしを引きとめました」と女は繰返して強調する。
緑の森でバラを摘んでいるところに妖精が現れてジャネットの処女を奪ったという話は、すでに第4話の『タム・リン』("Tam Lin", Child 39A)という作品でも紹介の通りである。『タム・リン』の場合には女の勇敢な振舞いで、出来た子供の父親が妖精界から人間界に連れ戻されたという話であったが、今回の話でも、別れる時にもらった数々の贈り物(金髪、黒玉の首飾り、金の指輪、小さな鞘付きナイフ)が証拠となって、森で出会った若者こそ、嫁いできたこの城の王様であったことが分かって、結婚に漕ぎ着け、ほどなく、かわいい男の子が生まれたのであった。
「ぼくはキリスト教国で/一番不幸な男です/「か弱くて優しい女に言い寄ったのに/孕(はら)み女を 娶(めと)ってしまった」とこの王は母親に訴えていたが、森で出会った時には「生娘かそうでないか」は構わなかったのである。男と女の本来の自由な出会いと、「結婚」という形式に介在する宗教的・道徳的拘束、あるいは、単なる風習との自己矛盾を、この歌は伝えようとしているのではないか。生まれた赤子の胸に、「ぼくの父の名は ギル・ブレントン」とはっきり書いてあったという終わり方には、眼に見えない作者のメッセージが秘められているように思われる。[直接的な関係は無いが、19世紀アメリカの小説家ナサニエル・ホーソンの代表作『緋文字』(1850)の主人公ヘスターの胸の文字 ‘A’ に連想が結びついてゆく。]
ひとくちアカデミック情報:
ナサニエル・ホーソン: Nathaniel Hawthorne, 1804-64. 代表作『緋文字』(The Scarlet Letter, 1850)の中で女主人公ヘスター・プリンは、17世紀ニューイングランドのピューリタン社会の中で姦通の罪を犯し、"A" (Adultery)の烙印を胸に生きてゆくことになる。しかし、その意味するところは、生涯にわたって消えることのない「罪」の象徴なのか、あるいは、へスターのその後の生き方を通してやがて「不変の第一原因、神の慈悲」、ローマ時代に裁判官が被告を無罪とする時に投じた"A"の文字、'Alpha and Omega'と表現される「キリスト」の意味、等々に変容してゆくものなのか、解釈は様々であろう。小説の出だしの章「獄舎の入口」に、「あかざ」 ("pig-weed")など「監獄という文明社会の黒い花」("the black flower of civilized society, a prison")の見苦しい雑草が生い茂っている中に「宝石のように優雅な」野ばらの花の茂みがあって、「こゝへはいってゆく囚人や宣告がすんで刑をうけに出てくる罪人を大自然の深い心があわれみそして親切をしめしているしるしに、その芳香とはかない美をささげているものと想像されるのであった」と書かれ、さらに、「この一輪の花が、物語の途中に姿を見せるやさしい心の花を象徴し、また人間のもろさや悲しみをのべる暗い結末を和げる役に立てばよいと願うことにしよう。」("It may serve, let us hope, to symbolize some sweet moral blossom, that may be found along the track, or relieve the darkening close of a tale of human frailty and sorrow.")と作者は結んでいる。[以上、日本語引用は鈴木重吉訳(新潮文庫)から、英語原文はThe Modern Library College Editions版から。]
この小説を念頭に置いた時、森で見知らぬ男に出会って結ばれて子供が出来たり、一輪のバラを摘んで妖精と出会ったりするという、伝承バラッドにおけるケルト的モチーフと、「結婚」という文明制度がもたらす「生娘」へのこだわりという構図は、何か人間の本能やもろさや悲しみを湛えた深い歴史に触れているように思われるのである。