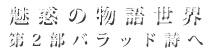第61話 「その枕辺へ入れるかしら」
「ウィリアムの亡霊」 ("Sweet William's Ghost", Child 77B)
家の者が皆寝静まった真夜中にクラーク・ソンダズがマーガレットの窓辺に現れて「ぼくがおまえにあげた/信念と真心を返しておくれ」と言う。マーガレットが「信念と真心は返せない/二人の愛は裂(さ)かれない/あなたが部屋へ入ってきて/頬(ほほ)と顎(あご)に接吻をしてくれなけりゃ」と応えると、ソンダズは「ぼくの唇はとても冷たい マーガレット/いまでは土の臭いがする/おまえの唇に接吻すれば/おまえの命は長くない」と言い返す。唇が冷たいとか、土の臭いがするとか、バラッドでは珍しく曖昧な表現をしているが、次のスタンザの「おんどりがたのしく鳴いている/野鳥(とり)が夜明けを告げている」という言葉から、男は墓場から戻ってきた亡霊で、夜が明ける前に墓に戻らなくてはならないというバラッドの定式化された設定であることが判るのである。マーガレットが、難産で死ぬ女の行く末を教えてくれなければ信念と真心は返さないと言うと(これも、女が妊っていて、今にも難産で死にそうだということの持って回った表現であるが)、男は「女の寝床は天国の/あらせいとうに囲まれて/神の御許(みもと)につくられる そして/いとしい人に出会うだろう」と答える。死んだら天国に行けて、そこで愛する人に会えるのだと言われて安心した女は、長い杖に真心を撫でつけて返すのであった。
 |
| 陣内 敦 作 |
ここまでのところは、バラッドに馴染んでいないと解りにくい点がある。そもそも歌のタイトルが「ウィリアムの亡霊」なのに登場する亡霊の名前がクラーク・ソンダズである。この歌ではA版からG版まで7つの版があるが、歌を代表するA版および他の5つの版で「ウィリアム」、ここで取り上げたB版およびF版が「クラーク・ソンダズ」である。このような名前の変更はよくあることで、これは、バラッドにおける固有名詞の固有性が意味をなさないという重要な特色の一例である。次に、信念と真心を返すという話であるが、死者と生前に交わした誓いを、このように杖になでて返すとか死者の身体の一部をなでて返すという儀式を行わないと、死者がいつまでも生者のところに戻ってきて、新しい恋人との愛の誓いを交わす邪魔をするという迷信がスコットランドにあったということを伝 えているようである。
実は今回は、わが人生における、研究の師であり、遊びの友であり、酒の友であった薮下卓郎氏の冥福を祈って書いている。第22話で取り上げた「ロード・トマスと色白のアネット」における、「ぼくの手もとに残るのは/炉端の肥った助平女」(原文 'And I sall hae nothing to mysell / Bot a fat fadge by the fyre')の名訳で名高い氏であったが、今回の歌の最後の数行でもまた、原文の素朴な言葉使いを美しい日本語に置き換えた氏の名訳を鑑賞いただきたい(原文は「原詩(英詩)の箱」を参照されたい)。死んだら天国に行けるという女の夢を打ち砕くがごとく、それでいて、蛆虫が湧く冷たい墓の中という「死」の現実を潔く受容する中での再会を、かくも美しく、静かに表現し切っているのである。
12 「その枕辺へ入れるかしら クラーク
その足もとへ入れるかしら
その脇へ入れるかしら
そこでわたしは眠りたい」
13 「この枕辺へは入れない マーガレット
この足もとへは入れない
でもこの脇には
女が眠る場所がある
14 「冷たい土がぼくの蒲団(ふとん)
それはまた経帷子(きょうかたびら)
ぼくの寝床は土の中
飢(う)えた虫たちと眠るのだ
15 「冷たい土がぼくの蒲団(ふとん)
それはまた経帷子(きょうかたびら)
露がおりたら
たちまち寝床はぬれそぼつ」
ひとくちアカデミック情報:
薮下卓郎:2014年3月30日逝去、享年76歳。公の追悼文は日本バラッド協会のホームページに掲載させていただいたのでそちらをご覧いただきたい。(http://j-ballad.com/essay/161-yabushita.html)
そこでは少々遠慮した、もっと個人的な交友録の一端をここに残したいと思う。関西人らしく酒の肴(あて)にこだわった彼は、博多の或る寿司屋で箱ウニを無造作に、安く、出してくれることに感激して、わざわざそこで飲むために通ってくるという時期が数年間続いた。九州は平戸の老舗旅館に、江戸時代、松浦藩のお姫様の輿入れのための性教育用に描かれたという畳一畳ほどの春画と書、それに「女護が島」の絵巻物があることをお教えすると、後日、(海外研修で私の留守中に)関西方面の親友数名を引き連れて再訪されていた。実は、酒席での「縦横無尽の薮下流話術」の実態は、頭の皺から下の皺までのばすという、トータルな人間への好奇心であった。氏の名誉のために、もうこれ以上は書くまい。氏ほど豊かな想像力の人を私は知らない。氏の名訳の数々が生まれた所以である。(氏は、1939年兵庫県生まれ。1966年京都大学大学院博士課程中退、神戸大学、京都大学を経て姫路獨協大学大学院教授)