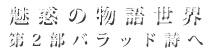第60話 金と娘とどっちが大事?
「絞首台から解放された乙女」 ("The Maid Freed from the Gallows", Child 95A)
今回採用の歌では、普通はもっともまとまりの良いA版でありながら、事件の動機も途中の経緯もすべて省略されていて、主人公の運命を決する最後の場面だけがうたわれる。絞首刑の判決を受けようとしているらしい女が、「善良な判事様 慈悲ぶかい判事様/ほんの少し お待ちください/柵のところに/馬に乗ったお父様が見えるから」と懇願する。
 |
| 陣内 敦 作 |
そして、やって来た父親に「お父様 わずかばかりのお金をください/わずかばかりの身代金を/私の体をあの墓から救うため/私の首を絞首台から救うため」と訴える。すると父親は、「おまえのために手放せる/金や土地などあるものか/ここにやってきたのは/おまえが吊されるのを見るためだ」と応えるのであった。以下、母親、兄、姉と、女の身内の者たちが次々とやって来るが、交わされる台詞は一言一句違わない繰返しである。最後に「愛(いと)しい人」がやって来て、女の同じ懇願に、「おまえのためなら/金や土地など惜しくない/ここにやってきたのは/おまえをなんとしてでも救うため」と応えて歌は終わる。
どの歌の場合でもチャイルドの頭注はヨーロッパ各国で流布している他版を紹介してくれていて、英語版の解り難さがある場合にそれを補う上で非常に助かるが、今回の場合、チャイルド自身が最も良くまとまっていると評している「王女シビリア」('Scibilia Nobili')を紹介してみよう。1874年にシシリー島で採録されたイタリアの歌である。アフリカ北岸に出没するイスラムの海賊が、王様の娘シビリアの結婚を知って、キリスト教徒に成り済まして屋敷にやって来る。戸口をノックするが、夫が狩りに出かけて不在のため新妻は戸を開けない。押し入った海賊たちは王女を連れ去る。戻って来た夫は海辺で、「妻の体重ほどの金」を身代金として支払うと申し出るが、海賊たちは「船一杯の金」でもダメだと言う。王女は、いっさいの食事も睡眠も拒否し、海賊たちが寝ている隙に海に飛び込む。引き戻された王女は、自らの身内の者たちとの交渉を申し出る。父、母、兄、姉から、いずれも拒否されるのは英語版と同じである。夫だけが「あなたさえ助かるのであれば全財産を失おう」と言うのも英語版と同様である。しかし、イタリア版には、因果応報の落ちがある。三日後に父親が死ぬと、娘は「死ぬがいいわ。赤い衣装をまといましょう」と言い、続けて同じ間隔を置いて母親、兄、姉と亡くなり、まとう衣装 が「黄」、「緑」、「白」と変わるだけで同じ台詞が繰返されて、最後は、「もしも愛する夫が亡くなる時は、黒い衣装に身を包みます」と言って終わる。
設定されている状況は違うが、私はここで、ラフカディオ・ハーンと 日本の子供たちのやり取りを思い出した。生徒が、「先生、西洋人は父と妻と一緒に海に落ちて自分だけが泳げる場合、まず妻を助けようとするそうですが、本当ですか?」「まあそうでしょうね」・・・「なぜですか?」「理由の一つは西洋人は男の義務は弱い者、とくに女と子供をまず助けるのが男の義務だと思っているからです」「西洋人は自分の父母よりも妻をより大事にするのですか?」「いつもそうとは限らないが — しかし一般的には、多分、そうでしょう」「先生、どうしてですか。それは私たちの観念からすると、たいへん道徳にそむきます」(「英語教師の日記から」平川佑弘編『明治日本の面影』講談社学術文庫, 43-44)
これらの話は、肉親よりも金、肉親よりも愛する者、いったいどちらが大切なのかと問いかけているのだろうか。確かに、今まで紹介してきた結婚と家族の反対にしても、身内の意向よりも愛するものを選択した悲劇、あるいは、その逆の選択をして後悔する話が多い。「歌の箱」で紹介しているナイルズ (John Jacob Niles)のYouTubeに寄せられたコメントに、「私の家(うち)では長いこと、ナイルズがうたうようなフォークで家族全員が、保守派も進歩派も、うまくまとまってきていました」("Folk music like JJN united the liberals and conservatives in my family for decades.")いう書き込みがあり、その意味するところは必ずしもはっきりとはしないが、ハーンと生徒のやり取りをめぐるようなこと、あるいは、イスラム教とキリスト教をめぐっての妥協の善悪といった話題で盛り上がることが家族の絆に貢献していたと言っているのだろうか。
ひとくちアカデミック情報:ラフカディオ・ハーン:Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904). アイルランド人の父とギリシャ人の母との間に生まれ、幼少時代をダブリンで過ごす。両親の離婚後、父方の大叔母に育てられたが、余りにも厳格なカトリック教育から、やがてキリスト教嫌いとなり、ケルトのドルイド教に傾倒していったと言われる。フランスやイギリスで教育を受けた後、1869年に渡米、ジャーナリストとして活躍する。1890年(明治23年)、アメリカの出版社の通信員として来日。そのまま英語教師として留まり、松江、熊本、神戸、東京と居を移しながら、日本の英語教育に貢献する一方で、欧米に日本文化を紹介する著書を多数残した。また、日本各地に伝わる伝説や幽霊話などに題材をとった作品『怪談』(1904)などの作家としてもよく知られている。後に東京帝国大学文科大学の英文学講師(1896-1903)。
「ケルト」という言葉は随筆「日本海の浜辺で」の中で、「バラッド」という言葉は東大での英文学講義の中で、いずれもハーンによって日本に初めて紹介された。