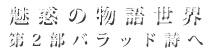第55話 「盗賊の妻になりたいか」
「バビロン」 ("Babylon or The Bonnie Banks o Fordie", Child 14A)
とある館の三人娘が森に花摘みに出かける。花を一輪摘んだ時、一人の盗賊が飛び出してくる。盗賊は一番目の娘の手をとって、「おまえは盗賊の妻になりたいか/・・・/でなけりゃ この匕首(あいくち)で殺された
 |
| Rackham, from Some British Ballads. 1919. |
いか」と迫る。娘は、「盗賊の妻になるくらいなら/・・・/その匕首(あいくち)で殺された方がまし」と答え、その場で殺される。次は二番目の娘、同じやり取りと同じ結果である。三番目の娘は姉たち二人とは違って、「盗賊の妻になりたくはない/・・・/匕首(あいくち)にかかって死にたくもない」という返事をする。更に強気に、「この森にはわたしの兄さんがいる/・・・/もしもわたしを殺したら 兄さんが仇(あだ)を討(う)つ でしょう」と言うのであった。盗賊がその兄の名を訊ねると、娘は「兄さんの名はバビロン」と答える。すると盗賊は、自分がその兄であると名乗り、「俺は何たることをしでかしたのか/おお とんでもないことをしてしまった」と言って、罪滅ぼしに匕首を取り出して自らの命を絶ったのであった。
前話で、バラッド伝承の過程で生まれる想像のるつぼを垣間見たが、人々が共有した想像の核心にはバラッド独特の物語の様式が存在する。第15話の「ひとくちアカデミック情報」で紹介した「臨終口頭遺言」、第31話の「バセティック」、第43話の'mystic number'、第44話の「誇張法」等々、いずれもバラッド様式を成立させている常套的な物語技法なのである。今回の歌で、三人の娘が森に花を摘みに行き、一輪摘んだ途端に危険な盗賊が現れるという設定も、絶対に行ってはならないと言われていた森に出かけて、バラの花を摘んだ途端に妖精が現れて処女を奪われたジャネット(第4話参照)と同じ様式の中にある。そういう意味で、バラッドに(未遂も含めて)頻出する近親相姦の歌も同じ様式化されたパターンであると考えることが出来そうである。古代エジプトの女王クレオパトラが弟のプトレマイオス13世と結婚 し、更にその下の弟のプトレマイオス14世と結婚したがごとき例を待つまでもなく、人類の歴史を遡れば遡るほど近親相姦は決して珍しいものではなかったことは容易に想像出来るし、私自身が或る本で、かつてバラッドを伝承した閉鎖的で等質的な社会の中で、しかも、厳しく長い冬の期間、娯楽の無い貧しい民衆の生活の中で、ある意味、必然的に生じうる出来事でもあっただろうと説明したことがある。しかし、そのような事実関係を想像するよりも、この「近親相姦」と いうテーマがバラッドに頻出するものであればあるほど、想像のるつぼの中での一つの確立した様式と捉える方が良いのではないかと思えるようになってきた。 それほど、様々な物語のバリエーションを生み出しているのである。次回からしばらく、そのような近親相姦の想像のるつぼを連続して覗いてみよう。
ひとくちアカデミック情報:
様式: バラッドには長い年月をかけて伝承されてきた中で創り出され、結晶化していった独特の物語形式があり、それらを一括総称してここでバラッドの「様式」(STYLE)という。上に言及した「「臨終口頭遺言」等々は、すべてその物語様式を構成する「技法」(TECHNIQUE)である。今回の歌で1行目と2行目の後に挿入されている「エイ ヴァウ きれいな//きれいなフォーディの堤で」(Eh vow bonnie // On the bonnie banks o Fordie)というリフレインもそのような技法の一つであり、事件の舞台を示すとともに、最初から最後まで変わらぬ美しい言葉と音の響きが悲しい事件(浮き世の変化)と 好対照をなして、独特の叙情性を生み出しているのである。このような様式が詩人個人によって生み出されたものでないことを、バラッドを鑑賞する際には絶えず心に留めておかなくてはならない。