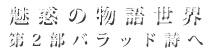第53話 滅びゆくものども
「ジョニー・コック」 ("Johnie Cock", Child 114F)
5月の朝ジョニー・コックは緑の森に鹿狩りに行こうとする。どういう理由(わけ)か、母親は悲し気に、お願いだから行かないでくれと嘆願するが、ジョニーは猟犬を連れて出かけて行く。ヒースの茂る荒れ野に一頭の鹿が見え、ジョニーの放った矢が脇腹に命中する。猟犬が、川の水際まで逃げた獲物の息の根を止める。「ジョニーは鹿を手早く裂いて/肝と肺を取り出して」、血に飢えた犬たちに与え、 ジョニーも犬たちも「鹿の肉をたらふく食べて/赤い血をたらふく飲み」、その後は、ジョニーも犬たちも死んだように眠ってしまう。
 |
|
Illustrated by Arthur Rackham, |
通りがかりにその様子を目撃した老人が森番に通報する。7人の森番の内でお頭格の男は、「もしそれがブレディスリーのジョニーなら/近づくのは無理だろう」 と言い、別の男は「もしそれがブレディスリーのジョニーなら/すぐにも殺したほうがいい」と主張する。結局、寝込みを襲われたジョニーは深手を負って闘い、7人中6人までを殺し、「残った男の肋骨三本へし折って/首の骨までへし折って/体を二つ折りにして」馬に乗せ、追い返す。何とも壮絶な闘いであった。その後、ジョニーはムクドリに、自分の死体を運んでくれるようにと、母親への伝言を頼む。「ジョニーのしなう弓は折れ/猟犬(いぬ)も皆殺されて/デュリスディアーに ジョニーの遺体は葬られ/ジョニーの狩りは終わりました」とうたい終わる。
スコットランド南西部の中心都市ダンフリースから北上、バラッドの舞台として名高い聖メアリー湖へ至るほぼ中間地点のラウザー・ヒルズの南西の一角にモートン城(1307年築城)と呼ばれた廃墟がある。この歌(F版)はスコットの『スコットランド国境の歌』(Minstrelsy of the Scottish Border, 1802-03)で紹介されたものであるが (スコット版のタイトルは "Johnie of Breadislee"; 'Breadislee'の場所未詳)、作品の頭注でスコットは、主人公ジョニーはかつてモートン城主であったこと、そして当時名代のアウトローで、禁猟区をものともしない鹿泥棒で、おそらく「ボーダー地方を根城とする、かつては高い身分でありながら身を滅ぼした者の一人であろう」と記している。
鹿泥棒をしたかどうかは別として、このスコットの言い回しから推測されることは、中世以来この地方を支配したクラン、マックスウェル家の第8代当主ジョン・マックスウェルである。縁戚関係に当たる第4代モートン伯ジェイムズ・ダグラス(1516-81)が、ある時期スコットランド王ジェイムズ6世の摂政(1572-78)を務めながら、女王メアリーの二番目の夫ダーンリー殺害に加担した廉で殺され、その後を継いで第4代モートン伯を名乗ったジョンは、その後、スペイン無敵艦隊の英国侵攻へ手を貸したという嫌疑で逮捕され、城は焼き落された。その裏には、頑固なカトリック派であったマックスウェル家追放の狙いもあった。廃墟と化したモートン城は、かつては国王をも凌ぐ力を誇っていたクランたちが新しい体制の力の元に滅ぼされてゆく運命にあったことの象徴的存在であったのかも知れない。同じように高貴な身分から森に住む無法者に転身したと伝説化されたロビン・フッド(彼も最後は騙されて命を落す。その作品については後日改めて。)を思い起こさせるではないか。
スコットランドの歴史マニアと言っても過言ではないスコットが、歌の主人公ジョニー(=ジョン;John→Johnie)がかつてはモートン城主であったというところまで述べながら、それが実在の誰を指すかということは言い淀んでいる以上、一介の他国人である私などが軽々に断定すべきではあるまい。ただ、ここで私が積極的に指摘出来ることが他に二点ある。編者チャイルドが類似の話は近いところにまとめるという編集方針であったことについては第51話で指摘しているところであるが、チャイルド115番以降集中的にまとめられている40篇にのぼるロビン・フッド関連バラッドの、いわば枕の形で114番「ジョニー・コック」は配されているのである。作品のメッセージ性としてその意味するところには深いものがあると思いたい。もう一つは、ジョニーと猟犬(いぬ)たちが、殺した鹿の血を飲む場面である。今日でも、スッポンの血をワインや日本酒で割って供する料理や、'black pudding' (あるいは、 'blood sausage')と呼ばれる豚や羊の血を固めて腸詰めしたものが世界各国にある(正直言って、最初にスコットランドに行ったときにこの料理に出くわした時にはいささか苦しい思いをした)。 実は私の子供時分に村の猟師が、捕まえてきた猪を小川の側で捌いて、開いた腹にたまっている血を丼で汲んでは飲んでいた場面をはっきりと覚えている。獲物の血をその場で飲むという光景を今日でも果たして見ることができるのかどうか詳らかでないが、血の中には命の力があると信じられていて、生きものから生きものへと命をつなぐ行為は、前話のアザラシ伝説にも通じる、人間と他の生き物たちとの共生の、大きなサイクルの中にあったのではないだろうか。
ひとくちアカデミック情報: ジョン・マックスウェル: John Maxwell, 8th Lord Maxwell, 1553 – 93. 南部の中心都市ダンフリース (Dumfries)の南11キロの海岸沿いに築城されたカルラヴェロック城 (Caerlaverock Castle)を拠点に、13世紀以降17世紀中頃まで南西部スコットランドを支配していた最強のクランであったマックスウェル家と、同じく中南部ラナーク地方を中心に一大勢力を誇ったダグラス家との関係、そして彼らのモートン城(Morton Castle)との関係が大変複雑であるから、説明の重複を含めて、あらためて整理しておこう。本文で紹介したマックスウェル家の第8代当主ジョン・マックスウェルは、6代当主ロバート・マックスウェル (Robert Maxwell, d. 1552)と第3代モートン伯ジェイムズ・ダグラス (d. 1548)の2番目の娘ビアトリックス・ダグラス (Beatrix Douglas)の次男であったが、第4代モートン伯ジェイムズ・ダグラス(第3代の3番目の娘エリザベスの夫)の死後、自ら第4代モートン伯を名乗ったのである。1458年創設の「モートン伯」の称号は代々ダグラス家のものであるが、第4代の死後、モートン城および 称号は一旦第7代のジョン・マックスウェルへ、そして第3代の孫に当たる第8代ジョンへと移譲された。1588年にスペインに行ったジョンは翌年のスペイン無敵艦隊(Spanish Armada)の英国侵攻への加担の廉で帰国とともに逮捕され、その年、ジェイムズ6世(スコットランド王, 1567-1625; イングランド王, 1603-25)が仕組んだ、頑固なカトリック派であったマックスウェル家追放の遠征隊によって城は焼き落され、剥奪されていた称号は再びダグラス家に戻された(にもかかわらず、ジョンは最期まで「第4代モートン伯」の称号に固執した)。翌年、ジョンは10万ポンドの保釈金で釈放され、国境警備の監督官に復するが、最後は、アナンデイルのクラン・ジョンストン (Clan Johhnstone of Annanndale)との抗争で命を落す。