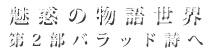第94話 人生は悲喜劇ドラマ
「ブラウン・ロビン」 ("Brown Robin", Child 97A)
王様の一人娘が酒席での接待をさせられているが、その眼は「庭で雨に打たれる/ブラウン・ロビンに釘付け」である。合間を縫って部屋に戻り、窓を開くと、ハープを弾いて、「お庭に小鳥が一羽/なんてきれいな声かしら/いつの日か/愛するあなたにお会いしたい」とうたい始める。すると恋人が「君の言葉が/嘘偽りのない真実ならば/美しい恋人よ/今宵君の部屋で会えるでしょうか」と応じる。娘は門番に酒を振舞い、酩酊した隙に門の鍵を手に入れて、恋人を中へと引き入れる。夜が明けて、朝日が部屋に差し込むと、ロビンは「すぐにも見つかるに違いない」と慌てるが、娘は「怖がることなどありません/うまく中に入れたのですから/うまく外にも出しましょう」と言う。急いで酒蔵に行き、ワインを飲んで酔った振りをしているところに、蔵に降りてきた王様とばったり出会う。どうしてこんなところでワインを飲んでおると咎められた娘は、「海を越えて贈られた/お父様のワインのせいで/頭はふらふら まるで船酔い/部屋にはとてもいられません」と答える。王様から、「外へお行き かわいい娘/外の空気を吸うといい/緑の森を散歩しなさい/侍女も連れて行きなさい」と言われて、まんまと娘は王様を騙すことに成功する。しかし、門番は手強い。「侍女なら森へ行ってもいいけれど/高貴な姫が森へ行くなど言語道断」と邪魔をする。自分には33人の侍女が付いているけれど、誰一人自分が欲しい花を知らないからと抗弁した娘は、恋人を侍女のように変装させて脱出しようとした時に、意地悪な門番が「森へ行く侍女の数を数えよう/戻った時に減っていないか確かめよう」と言う。変装して城を出るブラウン・ロビンの姿を目撃した王様の、「こりゃまた太った娘だわい」というセリフに続いて、「娘は五月の朝に出て行きました/良く晴れた朝でした/二度と戻ってきませんでした/老いた父は一人ぼっちになりました」と終わるこの歌には、一種のトラジコメディ(悲喜劇;tragicomedy)の味わいがある。
 |
| 陣内敦作 |
この歌のB版では、森に行った恋人たちの後を追った森番が茂みの陰からロビンを撃つ。娘は、門番が自分の一番好きな花を撃ったと王様に訴え、王様は娘に、門番を即刻縛り首にすると約束する。C版では、いったんロビンを連れ出した後、娘が城に戻ってくると、真相を見抜いた門番から「暴露するぞ」と脅される。黙っていてくれれば報酬は弾むと約束した娘は、気分が悪くなった侍女を迎えに行くと偽って再び森へ行ったまま、二度と戻ってこない。悲しむ王様に門番は、「誰も咎めないと約束されるならばお連れ戻しいたしましょう」と申し出る。王様は、「それが女であれ男であれ、決して咎めはしない」と約束し、連れ戻された娘と恋人ロビンはめでたく結婚することになる。門番は娘との約束通り、一生暮らせるほどの金銀を受け取った、となってこの歌は終わる。
このような異版の存在も、トラジコメディの成立に一役買っているのである。一般的に言って、伝承されたものの異版の数はその歌の一種の人気のバロメーターであると同時に、内在する物語の可能性の多少をも示していると言えよう。
ひとくちアカデミック情報:
トラジコメディ: 悲喜劇;tragi-comedy. 悲喜劇は、第二次大戦後のイギリス演劇ではサミュエル・ベケット (Samuel Beckett, 1906-89)やハロルド・ピンター (Harold Pinter, 1930-2008)などの不条理演劇と結びついていったが、元々は、喜劇や悲劇といった従来のカテゴリに分類しがたい、ある種のロマンス的な劇を意味した。また、エリザベス朝の詩人サー・フィリップ・シドニー(Sir Philip Sidney, 1554 – 86)は『詩の弁護』(The Defence of Poesy)の中で、当時の演劇事情について次のように述べている:「わが国の劇作家たちの劇はすべて何と正しい悲劇でも正しい喜劇でもないことでありましょう。そこでは王様と道化とが同居しておりますが、話がそうなっているからというのではなくて、道化は頭や肩をこづかれて無理やりに舞台へ押し出され、荘重な事件の中で一役を演じさせられるのでありまして、節度も分別もあったものではありません。ですから、かれらの雑種的な悲喜劇 (‘mongrel Tragi-comedy’)によっては、感歎と同情も、あるいは正しい陽気さも得られません。」(富原芳彰訳)
バラッドの世界というのは、単一の作品の中で、あるいは、複数の異版の形で、おおむね、ここに言う「雑種的な悲喜劇」がうたわれていると言えるかも知れない。しかし、それによってシドニーが言う「感歎と同情」が得られないのではなくて、今日まで延々とうたい継がれている一番の理由は、むしろ、様々な悲喜劇的局面こそ人生が織りなすドラマであるということを伝えているからではないか。
*データ管理上の都合により、コメント欄はしばらく非公開にさせていただきます。どうぞご了解くださいませ。